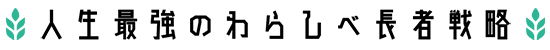わらしべ長者から教訓を得る
自分が「わらしべ長者戦略」を実現しようとあれこれ試したり、実現可能性をメンターに指摘されたりしているとき、この戦略のもとになった「わらしべ長者( 宇治拾遺物語 )」を何度も読んだ。
わらしべ長者で、もっとも率直に、人として決して忘れてはならない教えがあるとすれば、「困っている人に正しい方法で手を差し伸べる」という心構えだろう。
手を貸すことを厭わない
宇治拾遺物語のわらしべ長者は、お人好しとはいいがたい。悪人ではないのだが、困っている人が目の前にいても真っ先に駆け寄るようなタイプではない。相手に話しかける前に、遠目でじっくりと様子を観察し、「こういう状況なんだな」仮説を立てたうえで、話しかけにいくという用意周到さがある。
負けない戦をしないような性格だ。これは、宇治拾遺物語では単なる男ではなく、青侍(身分の低く若い侍)だったという理由もあるかもしれない。
とはいえ、目の前に困っている人がいて、自分がその人のために何かしてやれる状況だと見なせば、逡巡する間もなくすぐに手を貸している。
それは、相手にとっては願ってもないような、的確な助け舟である。
話しかける前に熟考するのは、自分が害されたり大損したりしないためという見方もできるが、「もっとも相手のためになることを自分がしてやれるのか?」を考えるためと捉えることもできる。古文で書かれた物語は、心情を細かく記すことがないので、こうやって考察する余地があるのも楽しいところだ。
深い善意があっても、真に相手のためになる判断が下せるかどうかは別問題である。
わらしべ長者は、相手の課題を正しくとらえ、解決の手段を提示したからこそ、相手は深く感謝し、その証として良いものを譲ってくれたのだ。
「長者」とは何なのか?
わらしべ長者の「長者」というのは、今では富裕層のことだと思われている。「長者番付」「億万長者」という形で使われていて、金を持っているというイメージが根付いたのだろう。
しかし、従来の「長者」には、かなりたくさんの意味がある。
一般的にイメージされるように、「金持ち」や「富豪」を指すこともある。「首相」や「主宰者」などのトップを指すこともある。
一方で、「徳の優れている人」、「他に恵みを与え、自らの徳を積む善行に優れた人」という意味もあるのだ。
鎌倉時代には仏教の影響が大きかったはずだから、徳のある人とか他に恵みを与える人というニュアンスを存分に含んでいると見ていいだろう。
実際、わらしべ長者の男は、困っている人に正しく手を差し伸べ続けた「長者」だった。善意に振り回されず、状況を読んで正しく善行を詰むような人間だったからこそ、誰もがうらやむ長者になれたのだ。
人間は、最も多くの人間を喜ばせたものが最も大きく栄えるもの。
徳川家康