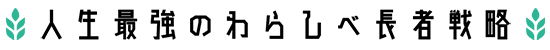わらしべ長者の落とし穴
わらしべ長者に関しては、成功した人よりも、失敗したエピソードを見つけることの方が容易だ。
わらしべ長者戦略にチャレンジしてみた体感と、いくつかの失敗例も見たところ、わらしべ長者の方法にはいくつか落とし穴があると気付いた。
もっとも失敗しやすい理由として、自分の立場を下にした状態で交換を提案してしまう、ということが挙げられる。
テレビ番組のわらしべ長者はなぜ失敗したか
例えば、とあるテレビ番組でわらしべ長者を検証したところ炎上している。高校生がこの日のために購入したワイヤレスイヤホンをフォトブックと交換したり、数千円のぬいぐるみを数百円のシールと交換するさまが不愉快だと言われたからだ。
子ども相手に舌先三寸で高価なものを奪う大人の姿は見苦しい。だが、これが親切な人ばかりだったところで、パッとしない成果のまま企画は終わったのではないだろうかと思う。
なぜなら、自分から下手に出て交換を”お願い”していたからだ。しかし、わらしべ長者では、男はほとんどの場合で交換時には対等か上の立場だった。モノをあげるかどうか自分の裁量で決められる立場だったのだ。
テレビの撮影では時間制限があるので、その辺で目に付いた人とモノを「交換する」ことを強いられる環境だったろう。テレビ的にも、物々交換に交渉術は不要という見方だったはずだ。
しかし、実際にわらしべ長者に成功している人々は、短くても1ヶ月はかけて慎重に物々交換の相手を選んでいる。モノが高価だと、なおさら慎重に人を選んでいる。モノについては実際に会って交渉もしている。この違いは大きい。
「交換すること」が目的になってはいけない
わらしべ長者の主人公も、交換する人を選んで成功を手に入れている。 お人好しに代えられている童話版でさえ、自分から「何かと交換してくれませんか?」と頭を下げて縋りついたことはない。加えて、何よりも自分より裕福そうな人としか取引をしていないことにも注目すべきだろう。
宇治拾遺物語では、主人公は別にお人よしではないので、いかにして成功がもたらされたのか分かりやすい。
わらをみかんに代えると、主人公はまず相手の出方を伺うようになった。交換できそうな相手をしばらく観察し、相手の状況を冷静に聞いたうえで、みかんや布や馬を差し出すという判断を下している。
馬と交換するときには自分から売り込んだが、馬を欲してそうな人を見つけて「買いませんか?」と初めから対等な取引を求めている。
どういう状況でも、「相手の助けになるものを譲る」と「自分にとって価値を見出せそうなものと交換する」という2点は(暴力に訴えられない限り)、童話でも宇治拾遺物語でも、決して譲ってはいないのだ。
相手のためになりたいという思いと、良いものと交換したいという野心を両立させたうえで、交渉相手を選ばなければ物事はいい方向へは進まないという教訓である。
人に対しては、寛大すぎても優しすぎてもいけない。交際上の優位を持つには、他人を何ら必要としないこと、そしてそういう素振りを見せること。
アルトゥル・ショーペンハウアー